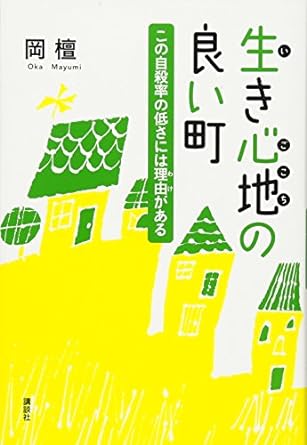徳島県旧海部町(2006年に合併し現在は海陽町の一部) 「自殺”最”希少地域」
少子高齢化の問題を抱えたどこにでもある田舎の典型、なぜ突出して自殺率が低いのか?
両隣に接する二町に対しても、海部町だけが突出して自殺率が低い。
自殺危険因子:自殺の危険を高める要素
WHO:社会経済的地位の低さ、失業、支援の欠如、精神疾患、病苦等
自殺予防因子:自殺の危険を緩和する要素
WHO:① 家族との関係、② 個人の素質や人柄、③ 社会文化的背景
日本人の自殺の動機=自殺危険因子
一位:病苦・健康問題、二位:生活苦・経済問題 これら2つで全体の70%を占める。
隣接する他の二町と比較して、海部町にも自殺危険因子は同じように存在していた。
つまり、海部町には、自殺予防因子が強くあらわれているということ。
町で見つけた五つの自殺予防因子
地理的には、住宅が非常に密集している。
自殺予防因子ー1 多様性重視の傾向
〜 いろんな人がいてもよい。いろんな人がいたほうがよい。〜
- 赤い羽根募金が集まらない。
- 老人クラブ加入率が周辺地域の中で最も低い。
- 「朋輩組(ほうばいぐみ)」海部町に現存する江戸時代からの相互扶助組織
特徴:いつでも誰でも入会・退会できる。入りたくないと言ってもなんら不利益を被ることがない。開放的で風通しが良い。
自殺多発地域であるA町との比較
- あなたは一般的に人を信用できますか?
→「信用できる」と答えた人の比率は海部町がより高い。 - 相手が見知らぬ人である場合はどうですか?
→いずれの町も信用度は低下するが、海部町の低下はより小さかった。
海部町は、相手が身内であるかよそ者であるかによって大きく態度を変えない。排他的傾向がより小さなコミュニティであると解釈できる。
自殺予防因子ー2 人物本位主義をつらぬく
〜年長者だからといって威張らない〜
海部町の「朋輩組」:中学を卒業した年長者が次々に入会し、年長者が年少者を抑えつけない。
他県にある「若者組」:最初の3年間がいかに忍従の日々であったかを口々に語る。
自殺予防因子ー3 自己効力感
〜どうせ自分なんて、と考えない〜
「自分のような者に政府を動かす力はないと思いますか?」の質問に「ない」と答えた比率
海部町で26.3%、自発多発地域A町で51.2%。A町では優位に政治に対する無力感が強い。
海部町:地方の小規模な町村には珍しく、首長選挙で長期政権の歴史がない。
自己効力感:出来事に対し影響力を持っていると感じること。=「有能感」「自己信頼感」
海部町:自己効力感を持つ人が多い。どうせ自分なんて、と考える人が少ない。
デイサービスでの会話
A町は深く険しい山間にあり、若い頃は家事や農作業の苦労話が笑顔で語られる。「うちら”極道もん”になったもんじゃ」(極道もんとは、働きもせずぶらぶらしている人)DSにも遠慮しがち。「ほんまは2回行きたいけど、1回にしている。極道もんと言われるから。」
ある海部町の精神科医師によると、海部町では大威張りでデイサービスに行く。
自殺予防因子ー4 リスクマネジメントの発想
〜「病」は市に出せ 〜
町の先達が言い習わしていたという格言。「体調がおかしいと思ったらすぐ開示せよ。周囲がなにかしら対処法を教えてくれる。」の意味。痩せ我慢・虚勢への戒め。「取り返しのつかない事態にいたる前に周囲に相談せよ。」
[どの町にも助け合いはある] 〜 相互扶助に関して 〜
海部町も自殺多発地域であるA町にも、どちらにも「助け合いの精神」は深く根付いており、日常生活によく組み込まれている。ただし、「助け合い」という言葉にも、その本質や住民意識に、地域によって差異がある。
海部町では、個々人が私的な悩みを開示しやすい環境づくりを大切にしてきた。
A町では、個人的悩みを誰かに相談することに強い抵抗を感じている。「近所に迷惑をかける。」昔から」強い絆で助け合って生きてきた。支え合わねば生活が成り立たなかった。だから、「助けてくれ」と軽々しく言えなくなってしまった。
[海部町のうつ受診率]
海部町と近隣町住民のうつによる受診率を比較すると、海部町がもっとも高い。
医師によると海部町からの患者は、軽症の段階で受診する場合が多い。
→うつの早期発見・早期対応というメカニズムが機能している。
海部町の老人達には、当事者を遠巻きにしたり、そっとしておいてあげようという発想があまりない。「ほな、見に行ってやらないかんな。」「あんた、うつになっとんと違うん。」
A町では、うつに対しての偏見が強く、直接本人に指摘することはあり得ないと言う。
自殺予防因子ー5 ゆるやかな絆
基本は放任主義で、必要があれば過不足なく援助する淡白なコミュニケーション。
[近所付き合いに対してのアンケート:日常的に生活面で協力し合っていると返答の割合]
海部町:16.5%、 A町:44.0% 海部町が大きく下回っている。
[人間関係が固定されていない]
- ちょっとした逃げ道や風通しを良くする仕掛けがある。
- 複数のネットワークに属している。
コミュニティにおける人間関係の硬直化を防いでいる。
[海部町の歴史]
江戸時代初期:材木の集積地。一攫千金を狙っての労働者や職人、商人などが流入。この町の成り立ちが周辺の農村型コミュニティと大きく異なる。多くの移住者によって発展してきた地縁血縁の薄いコミュニティ。ゆるやかな絆が常態化。
無理なく長続きさせる秘訣
〜 生き心地良さを求めたらこんな町になった 〜
1 ) 多様性重視がもたらすもの
社会=多様性という図式を刷り込まれ、それがデフォルトであると思って育つ。
スイッチャーという役割
関心を示さない、違う印象や異論を唱える、別の話題に変える者。
<いじめのある集団A>
居合わせたもの達がこぞって話の輪に加わり、表現の強さがエスカレート。
<いじめのない集団B>
集団の中にスイッチャーが存在する。
集団は多様な因子で構成された方が、スイッチャーの存在確率が高い。
2 ) 関心と監視の違い
海部町の人:他人に興味を持っている?の質問に、「興味津々やんなぁ」と。
「関心を持つ。」が「監視している。」のではない。
最初は、関心を持つが、やがて飽きて興味がなくなる。冷めやすい・飽きっぽい性格。良いことであっても悪いことであっても、その評価が長続きしない。
3 ) 弱音を吐かせるリスク管理術
援助希求:悩みや問題を抱えた時、周囲に対し助けを求めようとする意思、その行動。
助けを求める行為は、自分の弱みをさらけ出すことで、心理的抵抗が生じても不思議はない。
援助希求を肯定的にとらえるメッセージの発信が重要。
自殺率の地理的特性
徳島県:全国でも自殺率は低い方。→ 県が取り組む自殺問題は、優先率が低かった。しかし、A町での自殺率が極めて高いことも認識していた。近隣の地域格差が大きい。
⚪︎ 値が大きいと自殺率が高くなる地形特性
- 可住地地形斜度
- 最深積雪量
⚪︎ 値が大きいと自殺率が低くなる地形特性
- 可住地人口密度
- 日照時間
- 海岸部属性
A町は、険しい山間の集落で、一昔前は、近隣の民家を訪ねるのにも急斜面の曲がりくねった山道をつたっていく必要があった。隣人に対して軽々しく「来てくれ」「助けてくれ」と言えない気質を身につけている。つまり、隣人に迷惑をかけることを極力避けようとし、我慢強く克己心があり、私的な問題で助けてくれとなかなか言い出せない人たちのコミュニティ。
明日から何ができるか
自己効力感が低い状態の回避
明日から「どうせ自分なんて」と言うのをやめる。
行政がとるべき措置
短期的
⚪︎ ハイリスク群に標準を合わせる。
- 健康上の深刻な問題を抱える人々
- 経済的困窮に陥っている人々
- 最近大きな喪失体験を持った人々
- 精神疾患に罹患している人々
中長期的
⚪︎ 弾力性の高い思考や問題対処能力を身につけるための教育
⚪︎ 社会全体を対象とした啓発
自殺危険因子を軽減する努力をしながら、予防因子の強化に注力する必要がある。
”幸せ”でなくてもいい
海部町とその両隣に接する町を比較すると、海部町の住民幸福度は三町の中で最も低い。
つまり、驚くことに「幸せ」と感じている人の比率が最も小さい。しかし、「幸せでも不幸でもない」と感じている人の比率は最も高い。また、「不幸せ」と感じている人の比率も最も低かった。「幸せ」であることより「不幸でない」ことが重要と考えられる。
→ 何らかの理由により、幸せを感じられなくなった時の対処の仕方が重要ということ。
損得勘定を馬鹿にしない 〜 人の業を利用する 〜
「なぜ、海部町はこのようなコミュニティをつくり上げてきたのか?」
⇨「それが海部町市民にとって”お得”だったからです。」「損得の問題なんです。」
長い目で見れば損失を大きく減らせるという発想
人間の業である損得勘定を基にしてきたからこそ、長年に渡り破綻することなく継承されてきたと考えることができる。
自殺って、それほど悪いことなのでしょうか?
数年前に長女を自殺で失った初老の女性から尋ねられた。娘は、おとなしく、引っ込み思案だったが、自分のことより相手の気持ちをおもんばかる心優しい子だった。
親戚たちは、両親を責め立てた。「命を粗末にして。」「残された人の気持ちを考えなかったのか。」「死ぬ気になれば何でもできただろうに。」
これほどまでに責められるようなことを、あの子はしたのでしょうか?もし、病気や事故で死んだのなら、こんなことは決して言われなかったでしょう。「かわいそうに」って言ってもらえたでしょうに。娘を批判する声ばかりが聞こえてきた。
⇨自殺へと傾いていく人を一人でも減らしたい。しかし、自殺した人を決して責めない。
岡 檀 (おか・まゆみ)
和歌山県立医科大学保健看護学部 講師、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 研究員
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 博士課程修了
「日本の自殺希少地域における自殺予防因子の研究」で博士号を取得
コミュニティの特性が住民の精神衛生にもたらす影響について関心を持ち、フィールド調査やデータ解析を重ねてきており、その研究成果は学会やマスコミの注目を集めている。
第一回日本社会精神医学会優秀論文賞 受賞